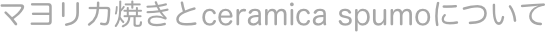ヨーロッパを旅した時に、明るい絵付けの施されたちょっと暖かみのある陶器を目にされることがありませんか?
おそらくそれがマヨリカ焼きという技法で焼かれたチェラミカ(陶器)です。
この技法は、その紀元を中近東の錫釉陶器に持ち、イスラム時代のスペインを経由してイタリアに、そしてイタリアからヨーロッパ中に広がった技法です。
素焼きの陶器にガラス質の不透明な白い錫(すず)釉を施し、そのガザガサとした乾いた釉薬の上に、水で溶いた色付きの顔料で絵付けをしてから再度焼成します。1000℃近くの温度で焼き上げられた陶器はガラス質の釉薬が顔料を取り込んで、何度洗っても雨にさらされても色褪せないカラフルな陶器に焼き上がります。
各国で呼び名は違いますが、スペインではマジョリカ、ポルトガルではアズレージョ、オランダではデルフト、イタリアではマヨリカ・・・などと呼ばれています。
特にイタリアでは、ルネッサンス期前にスペインからこの技法が伝わり、ルネッサンスの開花と共に、デザインや技法なども花開きました。ルネッサンス時代の技師や絵付け師たちがオランダやポルトガルなどヨーロッパ各地へ赴きその技術を伝え広めた、と言われています。ルネッサンス期には主に貴族に愛好された貴重なマヨリカ焼きですが、現在でもイタリア各地で多彩なデザインのマヨリカ陶器が焼かれ人々に愛されています。
文献の少ないマヨリカ焼きの歴史は少し謎めいていて、
例えばマヨリカの語源は、
①陶器が盛んであったスペインの「マラガ」から来ているという説と、
②スペインから陶器が輸出される際の経由地であった「マヨリカ島」から来ている
という説があります。
土から作った陶器全体のことを英語ではセラミック、イタリア語ではチェラミカ(ceramica)と呼びますが(イタリア語ではCEをチェと発音します)、磁器(石の成分が多い白い磁器土を使った硬質の焼き物・英語でポーセリン、イタリア語ではポルチェラーナ)との違いは、暖かみを感じる質感で、家庭での日常使用にも向いています。
マヨリカ焼きの特徴は、その暖かさと温もりと素朴な絵付けです。「土」が持つ温度感と「色彩」がもたらす華やかさは、人のぬくもりと決して華美でない明るさを演出します。
”磁器の持つ豪華な雰囲気も素敵だけれど、スローな生活に合う、ぬくもりある土で作られた「その器を使うだけで笑顔になれるような」器がもっとあってもよいのに”・・・・”漆喰風のシンプルで素敵なお家が増えている今日この頃、白い壁にマヨリカ焼きの表札やタイルやお皿で飾ったら素敵だろうな”・・・”イタリアでもだんだんと技術者が少なくなりつつあるマヨリカ焼きを、なんとか日本でも広めていきたい”・・・・。そんな想いを持って、2011年小さな工房「チェラミカ・スプーモ」をオープンしました。
チェラミカスプーモでは、日本ではまだまだ多く目にすることのないマヨリカ焼きを作成しており、材料(ビスク・土・錫(すず)釉薬・顔料など)は全てヨーロッパのマヨリカ用のものを使用し(<=残念ながら日本の土にマヨリカの釉薬は合わないのです)、日本の工房でひとつひとつ手描きで表札や食器に絵付けをして、皆様にお届けしています。
イタリア各地や世界で見たマヨリカ焼きにインスピレーションを受けてデザインしたサンプルは、全てオリジナルです。皆さまのインスピレーションも加えて、文字を入れたり、さりげなくメッセージを入れたり・・・自由にアレンジしていただくことも出来ます。
HPでご紹介出来るサンプルの図柄は多くはありませんが、別のカテゴリーのサンプルのデザインを他のものに応用することなども可能です。もちろん、全くのおまかせでも結構ですし、旅先でお撮りになった写真やオリジナルのイラストなどをお送りいただいて作成することも出来ます。ご自身のファンタジアを生かした、世界でひとつだけのチェラミカを、オーダーしてみませんか?
どうぞまずはページ一番上の各項目をクリックして、サンプル作品をご覧になってみて下さい。
(現在サンプルや作品の紹介は主にインスタグラムにアップしています。instagram : ceramica_spumo